こんにちは 経営学部の吉田靖です。
1月下旬、受験生は入試、大学生は期末試験。まさに『冬の陣』の真っ最中ですね。皆さんの奮闘が伝わって来ますが、今が踏ん張りどころです。寒いので体調にも気をつけましょうね。
勉強の時に使うのが教科書・参考書・問題集ですね。小学校以来、みなさんはどのくらいの本で勉強しましたか?今がこれらを集大成する時ですね。
大学に入学するとさらに教科書が増えますが、高校の数学の教科書はこれからも是非身近においてください。特に経営学部ではきっと役に立ちます。
さて、私は昨年、大学の授業でも教科書として使う本を共著で講談社から出すことができました。 『ExcelとRで学ぶビジネスデータサイエンス入門』です。高校生でExcelを使っている人は多いと思いますが、前半はExcelを使った株式等の分析方法をできるだけやさしく書いています。是非読んでみてください。表紙が黄色なのでこのブログのタイトルにしました。
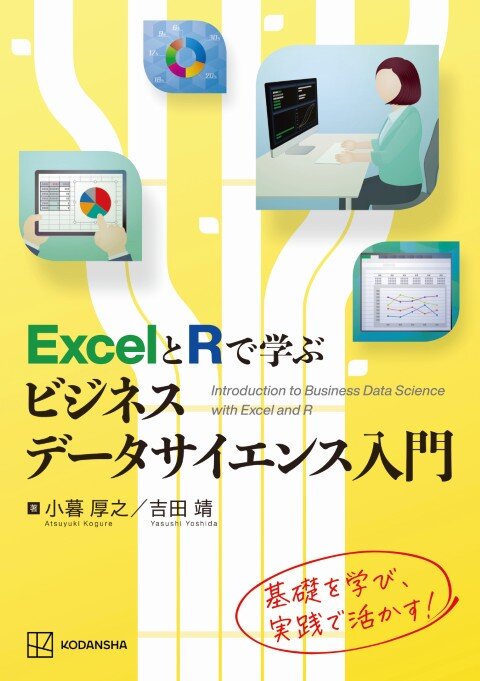
公的に提供されていないデータをファイルで提供しようとすると、著作権などいろいろな問題が起きます。しかし本書では、それをクリアできるデータを読者向けサポートウェブサイト(ここをクリック)に掲載しています。例えば、米国の株価指数のS&P500なども利用可能です。大学以前の金融経済教育の重要性が叫ばれているのに、日本の株価指数ではこのようなことができないことはとても残念です。
なお、東京経済大学はデータベースが充実していますので、学生になればものすごくたくさんのデータを教育目的で利用することができますので、安心してください。
この本の後半はRという誰でも無料で使える統計分析用のソフトウェアを紹介しています。このプログラムもサポートウェブサイトからダウンロード可能です。以前はこのようなプログラミング言語は少々敷居が高かったかもしれません。しかし、今は生成AIを使ってプログラムを作成することも可能で(本書ではAIの説明はしていませんが)、ずいぶん使いやすくなっていると思います。
データサイエンスの教科書といえば 『データ分析のための統計学入門』 (原著第4版、翻訳初版第4刷、原題: “OpenIntro Statistics Fourth Edition”、著者:David.M.Diaz, Mine Çetinkaya-Rundel, Christopher D. Barr、翻訳:国友直人、小暮厚之、吉田靖)という本も出しています(詳しくはこちら(日本統計協会のウェブサイト))。この本は、問題を解くことを中心とした解説になっていて、日本の統計学の教科書にはあまりないパターンです。ページ数の割には安価ですが、原著のPDF版はなんと無料を含む任意の非負の金額でOpen Introのウェブサイトでダウンロードできます。日本語版も出版されているものとは少し違いがありますが、翻訳者のうちの1人のウェブサイトからダウンロード可能ですので検索してみてください。私のゼミではこの本を使っています。
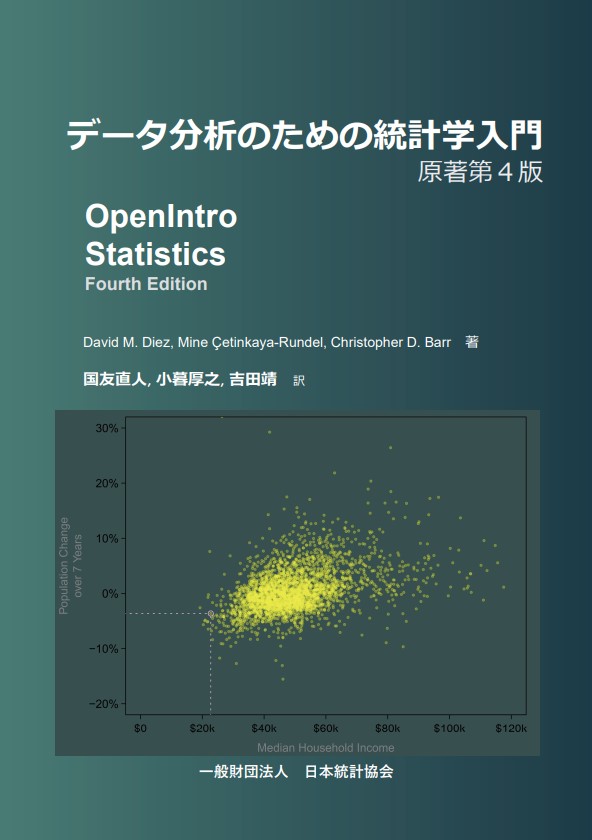

最後になりますが、日本証券アナリスト協会の第2次レベルのテキスト『証券分析とポートフォリオマネジメント』(詳細は日本証券アナリスト協会のウェブサイト)も多くの著者と共に執筆しており、毎年改訂しています。このテキストはファイナンスを勉強するためにとてもよい本なのですが証券アナリスト資格試験の第1次レベルに合格してから第2次レベルの受講を申し込んだ人だけに送られていますので、書店では販売していません。大学でファイナンスの勉強をして、金融機関などに就職したら是非ともチャレンジしてください。
それでは、授業でお会いしましょう。
吉田靖 (担当科目:経営財務論、ファイナンス論、ビジネスのためのデータサイエンス入門、ファイナンス・経営のための数理入門など)















