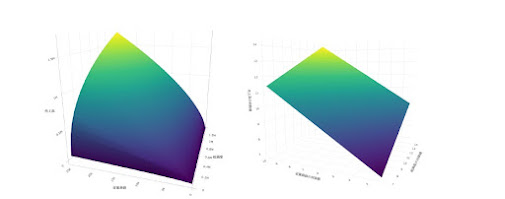本日は、アノマリーについてお話ししたいと思います。
10月27日に衆議院選挙がありましたが、この時、実に40年ぶりにあるアノマリーが崩れたことが話題になりました。
それは「選挙は買い」というアノマリーです。
アノマリーというのは、現在の理論の枠組みでは説明できなかったり、あるいは明確な理論的根拠があるわけではないのに、経験的に観測できる証券市場の規則性のことです。
「選挙は買い」もそうしたアノマリーの一つでしたが、衆議院の解散前日と投開票日直前の日経平均株価を比較すると、1979年から過去15回はすべて値上がりだったのに対し、今回は値下がりになったそうです。
アノマリーには面白いものもあり、「腕組みの法則」と呼ばれる、会社のホームページで社長が腕組みをしている企業は業績が伸びず、株価も下がるという法則だったり、サザエさん効果(日曜日に放送される「サザエさん」の視聴率が上がると株価が下がり、視聴率が下がると株価が上がる)、ジブリの法則(金曜日にスタジオジブリ作品が放送されると、週明けの株式相場が大幅に下落するという法則)なども知られています。
ここまで来ると、いくら理論的に説明できない現象であるアノマリーとはいえ本当にそんな現象があるの?という疑問が湧きますが、サザエさん効果については、大和証券グループのシンクタンクである大和総研の2005年のレポートで報告され、2006年には『サザエさんと株価の関係―行動ファイナンス入門―』として出版され、そこでは、「サザエさん」の視聴率とTOPIXの関連性を見ると、NY株との関連性よりも強かったそうです。
こうしたアノマリーが「現在の理論の枠組みでは説明できない」とされるのは、伝統的かつ標準的な経済学においては、「人はみな合理的な選択をする」というのが基本的な考え方の前提となっているためです。
しかし、皆さんも実感があるでしょうが、人間というのは常に合理的な行動を採るわけではありません。
そうした、現在の理論の枠組みでは説明できない行動や、明確な理論的根拠があるわけではない「非合理的」と思われる行動がもたらす現象について、「人は常に合理的に行動するとは限らない」という前提に立って考えていく学問を、行動ファイナンス理論といいます。
例えば、あなたの目の前に、以下の二つの選択肢が提示されたとしましょう。
選択肢A:100万円が無条件で手に入る。
選択肢B:コインを投げ、表が出たら200万円が手に入るが、裏が出たら何も手に入らない。
選択肢Bは50%の確率で200万円が手に入りますが、50%の確率でなにも手に入らないわけですから期待値は、200万円×0.5+0×0.5=100万円となります。
つまり、実はどちらの選択肢も手に入る金額の期待値は100万円で同額なのです。
しかし、この質問を実際に行うと、一般的には、堅実性の高い「選択肢A」を選ぶ人の方が圧倒的に多いとされています。
これは、人間は目の前に利益があると利益が手に入らないというリスクの回避を優先するためであると考えられています。
もちろん、人間には様々な性格がありますから、「自分は運が良い人間だ」と思える自信過剰な人であれば、仮に200万円が手に入るリスクが5%だったとしても、そちらを選択するかもしれません。逆に、「自分は運が悪い人間だ」という風に思う人であれば、期待値が低かったとしてもリスクの少ない方を選ぶかもしれません。
このように、様々な心理的または感情的な要因に従って行動を選択する人間が存在する結果が、証券市場のアノマリーとして表れてくると考えられます。
行動ファイナンスの登場は、従来の学問の理論的な枠組みから排除されていた人間や組織の非合理性であるが自然な反応を,学問の枠組みで再び考え直してみようという取り組みであると評価できます。
世の中は多様性(ダイバーシティ)と受容性(インクルージョン)が重視されていますが、行動ファイナンスの登場は、学問の枠においても、この世界には多様な人間が存在することを受け入れ、それぞれの個性がどのような影響をもたらすのかを考えるようになってきたといえるかもしれません。
(文責:経営学科 板橋雄大)